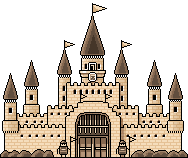<ぶらり岸和田>
和泉国守護であった楠木正成が甥の和田高家を岸和田に派遣して岸和田古城を築かせた。
「岸」と呼ばれていた当地に和田氏が城を築いたことによって
「岸の和田」と呼ばれ、「岸和田」へ変化したと言われている。
【岸和田城】
別名 「猪伏山滕(ちきり)城」 と呼ばれる。
岸和田城は猪伏山と呼ばれた小高い丘の上にあり、本丸と二の丸を合せた形が、
機の縦糸を巻く器具「縢」(ちきり)に似ていることから
蟄亀利城(後に千亀利城)と呼ばれるようになった。
また、「猪伏山」とは城全体の高台が猪が伏せた形に似ている
ことから付けられた呼び名という。
岸和田城といえば岡部藩、と地元の大半の方が答える。
事実、徳川家光の時代に岡部宣勝が城主になって以来、
明治維新迄13代に渡る岡部公の治世の元に現在の岸和田の街の基礎が固められたと言ってよい。
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

岸和田城 |
現在の天守は昭和29年に
市民の寄付や旧城主の子孫である
岡部氏の要望などにより再建
 |

犬走り石垣 |
本丸を取り囲む石垣の南面から東面にかけて、
「犬走り石垣」と呼ばれる周堤帯があるが、
軍事的には本丸へ攻め寄せる敵に
拠点を与えるという矛盾した造りであるため、
他の城では見られないものである。
これは岸和田城の石垣が「和泉砂岩」と
呼ばれるもろい石を多く用いているため
壊れやすく、強度を補強する為に
作られたものであるという。 |

八陣の庭 |
本庭園は、上・中・下3段の基壇の中央に、
大将の石組みを配置し、
これを中心に8つの石組みが
円形に配置されています。

竜陣と大将 |

岸和田だんじり会館 |
だんじりとは祭礼で奉納される山車のことで、
特に西日本で呼ばれることが多いそうです。
 |